リチャード・マシスン『ある日どこかで』 [本]
映画でも小説でもSFのなかで特に好きなジャンルは、サイボーグものとタイムトラベル(タイムスリップ)もので、壮大なスペースオペラなどはさほど好まない(嫌いではないが...)。
特にタイムトラベルものは、幼少の頃から米テレビドラマ『タイムトンネル(The Time Tunnel)』 (1966-67)にハマっていた。公園のタイヤの遊具などをくぐり抜けながらタイムトンネルごっこして遊んでいた記憶がある。
もちろん、最近ではTBSドラマ『JIN-仁-』も欠かさずに観ていた。
変ったところでは、コミックはあまり読まないが『テルマエ・ロマエ』(THERMAE ROMAE)3巻を持っている。
タイムトラベルもののSFは小学生の頃に古典ともいうべきH.G.ウェルズ『タイムマシン』を読んだ。中学生の頃は堂々とポルノ小説など手にすることができなかったのでエッチ描写読みたさにロバート・シルヴァーバーグ『時間線を遡って』も読んだ。
大学生になって観念的なタイムトリップものとしてはコリン・ウィルソン『賢者の石』にハマった。
映画では、ポップな『バック・トゥ・ザ・フューチャー(Back to the Future)』三部作(1985年、1989年、1990年)は楽しんだし、いかにもB級作品であるがジャン=クロード・ヴァン・ダム主演のSFアクション『タイムコップ(Timecop)』(1994年、米)も面白かった。最近ではデンゼル・ワシントン主演『デジャヴ(Déjà Vu)』(2006年)が面白かった。
タイムトラベル(タイムスリップ)に切ない恋愛が絡んだファンタジー作品として好きなのが、リンゼイ・ワグナーがヒロインを務めたTV映画『過去へ旅した女 (The Two Worlds of Jenny Logan)』(1979年)とともに、クリストファー・リーヴ主演の『ある日どこかで(Somewhere in Time )』(1980年)である。
映画『ある日どこかで』はずいぶん昔にテレビで観たきりで、ええ映画やったなぁ~という曖昧な感想しか残っていなかったが、梅田の旭屋書店の文庫コーナーで原作本『ある日どこかで(Somewhere in Time )』(リチャード・マシスン作・尾之上浩司訳・創元推理文庫)を見つけて買ってあった。
長いこと本棚で眠らせていた本であるが、1ヶ月前に村上春樹本の読後に何となく手にとって読み始めた。
『ある日どこかで』はタイムマシンなどSF的な道具立ては登場しない。かといって『賢者の石』のように観念的なトリップではなく、あくまでも念力というか強い自己暗示によって主人公の脚本家リチャード・コリアがリアルに1971年現在から1896年(映画版では1980年から1912年)にタイムトラベルするのである。
リチャードはあるホテルのホールの壁に飾られていたいにしえの舞台女優エリーズ・マッケナのポートレイトに運命的なものを感じて一目惚れした。彼女のことを調べていくうちに、過去に自分が彼女に会って彼女の人生に影響を与えていた形跡を見つける。そして彼女と会うために過去に遡ろうと試みる。
見ようによっては、過去の美人女優のもとにタイムトラベルしてまで押しかけて行き、周囲の妨害を他所にストーカー行為を続けて、やがてモノにする...というお話である。
映画版では作者リチャード・マシスン自身が脚本を担当しており、音楽や小道具などの伏線もすっきりとハマってわかりやすいロマンティックなラブロマンスにまとまっている。
原作は映画に比べると冗長でまとまりに欠ける印象であった。
タイムトラベルできるまでの経緯が長いし、主人公が彼女に出会ってからもふがいなくオタオタしている様子が事細かに描かれ過ぎている。
よくまとまった映画版を知っているだけに、彼女と結ばれるようになるまでがじれったく少々イライラしながら読んでいた。
逆に小説ならではの楽しみで、何日もかけて読みながら甘美な・幸福な気分に浸っていられた。
映画版では、1912年当時にまだ作曲されていなかったラフマニノフのラプソディ(『ピアノとオーケストラのための《パガニーニの主題による狂詩曲》』(1934年))の第18変奏:Andante cantabileの甘美なメロディをリチャードがエリーズに口ずさむシーンが鍵になっており、映画のテーマ曲としても効果的である(もっともラプソディを通して聴けば、パガニーニのヴァイオリン独奏曲『24のカプリス』第24曲をもとにした変奏曲で、諧謔(かいぎゃく)的な曲調で甘美というよりは辛口の曲なのだけど...)。
小説版では、リチャードの好きな作曲家がマーラーで、とくに交響曲第9番(1908年)の第4楽章 Adagioが引用されている。エリーゼはリチャードの影響で1896年当時のアメリカであまり一般的とはいえなかったマーラーを好むようになったというだけで、音楽は大きな鍵にはなっていない。
ちなみに小品というべき映画でマーラーを使うのはあまりにたいそうだったので、作曲のジョン・バリーがより親しみやすいラフマニノフのラプソディーを提案したそうである。
たしかにマーラーの交響曲第9番 Adagioは美しい曲ではあるが深淵な音楽なので、ラブロマンスには不向きである。ラフマニノフの甘美なメロディーがあってこそ成功した作品だと思う。
映画『ある日どこかで』 予告編(メインテーマ作曲:ジョン・バリー)
ラフマニノフ『パガニーニの主題による狂詩曲』より第18変奏:Andante cantabile
マーラー:交響曲第9番 第4楽章 Adagio
バーンスタイン指揮 ウィーン・フィル
「船に乗れ!Ⅲ ~合奏協奏曲~」 [本]
最近のボクの、集中力に乏しく、読書スピードの遅いのにしてはよく頑張って読めた...というよりは引きずり込まれた本だった。

ボクのⅠ巻、Ⅱ巻のレビューでは触れなかったけれど、チェロ専攻の音高生サトルの物語には「クラシック音楽」以外にもう1つの大きな柱・・・「哲学」がある。
早熟でクソ生意気なサトルは小中学生のときから文学作品に親しんだり、哲学書を読み耽っていて、そんな自分を特別な存在と思っていたり、ちょっと世の中を斜めに視ているような少年だった。
Ⅰ巻では少しばかりニーチェにかぶれている。
サトルは哲学志向によって倫社の先生と意気投合するが、Ⅱ巻でははからずもその先生に裏切りともいえるひどい仕打ちをして運命を狂わせてしまう。
それはサトルのその後の大きな心の重荷にも自己嫌悪にもなっていて、ニ十年後の「現在」も引きずっている。
Ⅲ巻の終わりで「船に乗れ!」の題名が先生に教えられたニーチェの言葉であったことが明らかにされる。そして自分や仲間たちのその後を述べながら、波に揺られるのが人生の試練であり、不安定・不確実な自己を意味しているようなことを語って「船に乗れ!完」と本篇が締めくくられる。
いったん本篇が完結した後で、『再会』という後日談が用意されている。これがけっして蛇足ではなくてすばらしいエピローグである。
長い間触れてなかったチェロを修理に出して、プロのフルーティストとして活躍している友人のリサイタルに行く。そして許せなかった昔の自分と向き合って...と、とてもステキなエンディングだ。
本篇だけでも十分に青春小説としてはまとまっているのであるが、本篇でスッキリしなかったものが『再会』によって「落としどころ」に落ち着いたように思う。
ところでボクはこの小説でどうしても馴染めない点がいくつかある。
「おじいさま」「おばあさま」・・・ふつうに「祖父」「祖母」と書いてほしいところであるが、あえて主観的な人称によって主人公の「育ち」を際立たせた表現だろうか?、
いかに育ちがよくて音楽の専門教育を受けていようとも、三流の音高生で、自分の才能の限界にぶつかったサトルは、けっして「憧れ」の対象でも「羨ましい」存在でもありえない。「のだめ」に出てくるヒロイン・ヒーロー像とは真逆の青春像だ。むしろ大多数の「ふつう」のコースを進んできたボクたちよりもその人生は辛く苦しいものであっただろう。
ただ、そんなに育ちがよくなくても、専門的に音楽をやってなくても、哲学にかぶれていなくても、ある種の「理想」「夢想」を抱きながらも、現実や自分の能力の限界に妥協せざるをえなかった多くの人たち・・・「ふつう」のボクたちにも十分に共感できる青春像であったと思う。
文体も気になった。基本的には「だ・である調」というよりも軽めの「だ・した調」というべき文体で淡々と語られている。ところがN饗奏者でもあるチェロの先生の所作については必ずと言っていいくらいに「おっしゃる」「なさった」という丁寧語が使われているところが鼻につく。音高の他の先生では使われていない表現で、たぶん作者の実体験があっただけに、チェロの先生に対する尊敬の気持ちが込められてしまうのだろう。
Ⅲ巻の楽曲は、
・音高3年生の発表会の「合奏協奏曲」としてバッハの「ブランデンブルグ協奏曲第5番」
・音高オーケストラの課題曲のモーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」
の練習風景や本番の演奏風景が克明に描かれている。
とくにブランデンブルグ協奏曲の本番の演奏場面は圧巻だ。才能あるフルートの親友とヴァイオリンソロの白熱したかけ合いは手に汗握る。
バッハ ブランデンブルグ協奏曲第5番 第1楽章 Allegro
バッハ ブランデンブルグ協奏曲第5番 第2楽章 Affettuoso 第3楽章 Allegro
カール・リヒター指揮・チェンバロ ミュンヘン・バッハ管弦楽団
音高オケの「ジュピター交響曲」本番では物語がクライマックスに達する。
モーツァルト「ジュピター交響曲」はボクもアマオケで演奏経験があるだけに、作中でサトルがこの曲の難しさを語っている場面は手に取るように理解できた。
YouTube動画はボクがCDでも持っているテイト指揮イギリス室内管弦楽団の演奏である。かつてサントリーホールのこけら落としシリーズのコンサートで、内田光子のピアノ協奏曲とともに実演に接した組み合わせである。
現代的?なピリオドアプローチではないけれど、ボクにとってはモーツァルト演奏の理想像である(めんどくさいから全曲貼り付けちゃえ!)。
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」 第1楽章(1/2)
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」 第1楽章(2/2)
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」 第2楽章
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」 第3楽章
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」 第4楽章
ジェフリー・テイト指揮 イギリス室内管弦楽団
「船に乗れ!Ⅱ ~独奏~」 [本]
出荷前の装置の仕上げに掛かりきりだったので、連休の醍醐味を味わうどころか、ふだん以上にきつかった気がする。
それでも、5月1日は息子のヴァイオリン教室の発表会に行くことができて、実家の母(息子の祖母)も招待して、ちょっとばかりは親孝行らしいこともできた。
本来ならば息子のヴァイオリン演奏の動画をアップして記事にしたいところであったが、息子はモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番という大曲に負けてしまって撃沈! 暗譜が真っ白になってピアノ伴奏だけが流れていく...今までの発表会にはなく可哀想な結末だった。父親としても呆然とする息子を前にして辛かったので、これ以上は触れないでおこう。
発表会の後は母も連れて家族全員で湖岸道路を少しドライブしてから日帰り温泉にも行って、休日らしい1日を楽しんだ。
連休のちょうど1週間前は、群馬への出張の行き帰りの新幹線の中で藤谷治 作「船に乗れ!Ⅱ ~独奏~」(ポプラ文庫ピュアフル)を読み終えた(今はⅢ巻を読んでいる)。
前にも紹介したⅠ巻では、チェロ専攻の音高1年生の津島サトルの希望にあふれる活き活きとした学園生活が明るく描かれていた。
Ⅱ巻ではサトルのラヴロマンスに焦点が当てられるが、やがて音高2年生になって、それが可哀想な展開になってしまう。
そういえばⅠ巻のプロローグに
ボーイング747に乗っていたら「ノルウェイの森」がながれてきたわけでもない(引用)
と書かれていたのを深い意味もなく読み過ごしていたが、Ⅱ巻に到って納得した。
「ノルウェイの森」さながらに悲劇的なわけではないが、Ⅱ巻の終わりのほうはサトルの暗く屈折した心境の変化に読むのが辛くなってきた。それでも読ませるところは作者の自伝的作品らしく強い説得力が込められていたからにほかならないだろう。
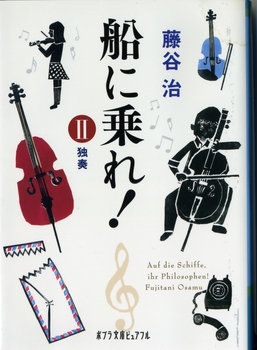
Ⅱ巻でもクラシック名曲が関わってくる。
サトルがモーツァルトの歌劇「魔笛」公演のタダ券を手に入れて彼女をデートに誘ったときのロマンティックな楽曲解説が印象的である。
「魔笛」の主人公タミーノとパミーナが「炎の試練」と「水の試練」を乗り越えていく場面・・・これをサトルが自分たちの恋愛に重ねようとしているようにも思える。
モーツァルト:歌劇「魔笛」第2幕より「炎と水の試練」の場面
サトルの友人・フルーティストの伊藤くんの発表会のバッハのフルート・ソナタ・・・ここではサトルがチェンバロ以外に伴奏に加わるチェロでアンサンブル組んだ。
J.S.バッハ:フルート・ソナタ イ長調 BWV1032 (1/2)
J.S.バッハ:フルート・ソナタ イ長調 BWV1032 (2/2)
エメニエル・パユ(フルート)
サトルがチェロのレッスンで取り組む課題曲の1つがフォーレの「エレジー」。ボクも大好きな曲で、ヴァイオリンで練習したこともある。哀愁の漂う曲だ。
フォーレ:「エレジー」
ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ)
2年生になってからは、音高オケでサトルがチェロトップを弾くようになって、課題曲がリストの交響詩「前奏曲(プレリュード)」だった。この曲の難度の高さにオケのメンバーは辟易する。
大編成のアマオケでもよく取り上げられる曲で、ボクは弾いたことはないが聴き馴染みのある曲である。
リスト:交響詩「前奏曲(プレリュード)」 1/2
リスト:交響詩「前奏曲(プレリュード)」 2/2
ダニエル・バレンボイム指揮 ウェスト=イースタン・ディヴァン管弦楽団
「船に乗れ!Ⅰ ~合奏と協奏~」 [本]
出張先で大型書店で時間を潰せることもあるが、売れ筋しか置いてないような小さな書店でも意外と「出会い」があったりする。

藤谷 治 作「船に乗れ!Ⅰ~合奏と協奏~」
まず「ポプラ文庫」というのを知らなかった。ポプラ文庫というのは最近刊行されたみたいで、とくに「ポプラ文庫ピュアフル」というのは青春小説をメインにシリーズ化されているみたいで、ちょっと手に取るのが気恥ずかしかった。
この藤谷治という作家も「船に乗れ!」三部作も初めて知った。
この作家は音高でチェロ専攻だった人で、自らの音高時代の経験をもとに「青春小説」として書かれた小説である。
音楽的な家庭で育ちのいいちょっとクソ生意気なお坊ちゃん(主人公=津島サトル)が私立の高校音楽科に進学して...というあたりは、共感もしないし馴染めない。勝手にやってろや!という気持ちである。
でも、あまりレベルが高いとはいえない音高オーケストラのドタバタした練習風景や、憧れのヴァイオリン専攻の彼女と室内楽を組むところの期待や緊張感は、ボクのアマチュアとしてオケや室内楽の経験と重なって、読み進んでいるうちにのめり込んでしまった。
おとついの三原出張の新幹線のなかでⅠを読み終えて、「船に乗れ!Ⅱ~独奏~」に移った。きのうは医院の待合でも夢中になって読んでいた。
おそらくコミック・アニメ・ドラマ・映画の「のだめカンタービレ」が好きな方なら、楽しめる小説だと思う。
この手の音楽小説が楽しいのは、ストーリーや登場人物だけではなく、作中に絡んでくる名曲解説の魅力が大きい。
サトルの通う音高の学長でもある祖父がホームコンサートで弾くオルガン曲-バッハのコラールBWV605、615は、ボクのWALKMANにも入れていたので車中で聴きながら読んでいた。
サトルが初めて経験する音高オケの課題曲はチャイコフスキー「白鳥の湖」からの抜粋で、こちらはボクがあまりそそられる曲ではないが、指揮者やトレーナーに厳しくしごかれ、罵られながら本番を迎える流れが面白い。
そして、サトルが憧れの彼女と、ピアノの美人教師と組んだトリオで演奏するメンデルスゾーンのピアノ三重奏曲第1番・・・この曲に対する作者の思い入れの深さがにじみ出てくる。
ボクはロマン派の室内楽をあまり聴かなくて、この曲も知らなかったので、読んでいるだけではイメージできなかったが、あのヴァイオリン協奏曲や交響曲「イタリア」、歌曲「歌の翼」などメロディーメーカーと知られるメンデルスゾーンの甘美さを想像していた。
サトルが聴き込んでいたのはカザルス(チェロ)の「ホワイトハウスコンサート」ライブ盤LPであったが、YouTubeではカザルスがコルトー(ピアノ)、ティボー(ヴァイオリン)と組んだ演奏がアップされていた。
思ったほど旋律美の曲だとは思わないが、メンデルスゾーンらしく気品と内省的な情熱を感じさせる曲だと思った。
カザルス・トリオによるメンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番
第1楽章
第2楽章
第3楽章
第4楽章
ヘッセ「荒野のおおかみ」 ≪長文≫ [本]
ボクは関西のメーカーに就職して間もなく東京転勤になった。せっかく大阪で友人と立ち上げた市民オケにも別れを告げて、馴染みのない東京に出てきた。
今から思えば社会人としては何にもわかっていない「小僧」であったろうが、一人でポツンと電気部品の試作・実験に明け暮れ、職場の人間関係には馴染めないで孤立していた。
そんな当時ボクの心の支えになっていたのが、読書と音楽であった。
インターネットなどなかったから、休日は神保町の書店街で過ごすのが楽しみだった。学生の頃から馴染んでいたヘッセやユング、音楽書などを買い漁っていた。
音楽はどちらかというと「聴く」よりは「弾く」ほうが好きだったので、転勤直後に入れそうなアマオケを探した。雑誌「音楽の友」の募集広告を見て、カタチばかりのオーディションを受けて、アマチュア・オーケストラ「東京ロイヤルフィルハーモニーオーケストラ」に入団した。
50人くらいの団員数、トロンボーン・チューバは入れない方針の二管編成オーケストラで、ハイドン・モーツァルト・ベートーヴェンなどの古典派音楽をメインにし、音楽監督・常任指揮者は置かずに団員が自発的に運営するポリシーのアマオケであった。
ここでの音楽経験によってボクの音楽の嗜好が固められて現在に到っている。
残念ながらこのアマオケは後に解散してしまったが、ボクの青春時代の思い出としてずっと心の中に残っている。
アマオケなので、ただ合奏練習して演奏会に臨むだけではなく、たくさんの雑用、準備、手配、お金の遣り繰りなどすべて自分たちで分担して運営していた。
人との交渉事が苦手なボクは楽譜の手配や配布資料の準備、パーティーのときは会場の飾りつけなどを率先してやっていた。
そうして回ってきた仕事の1つが、機関誌「カフェ・ロイヤル」の編集・発行であった。

機関誌「カフェ・ロイヤル」創刊号
その創刊号を膨らませるのに代表の抱負やコンマスの思い出話の他に何かネタをと思って書いたのが、ドイツの作家・詩人のヘルマン・ヘッセに関する駄文である。
内面的にはどこか尖がっていた当時のボクが、クソ生意気に知ったかぶりや受け売りでムキになって書いていたようだ。
それでも、オケのメンバーは、モーツァルトに傾倒して大編成のロマン派音楽を避けていたような人が多かったので、小難しいゴタクを並べたような青臭い記事でも評価してくれた。
テーマとして取り上げた映画「ステッペンウルフ/荒野の狼」は現在は国内でDVD販売・レンタルされていないようである。Allcinemaのサイトではロクな記事が出ていない。
Goo映画ではまだまともに取り上げられている。
オリジナルの文章は、縦書きのワープロ書きで改行が少なくブログ向けではないが、引用の注釈以外はほとんどそのまま掲載する。
* * *
ヘルマン・ヘッセの憧れと混沌の世界
― 映画「ステッペンウルフ」を観て ―
「荒野のおおかみ」に到るまで
恋愛のことを語るとなると ―― この点で私は生涯、少年の域を脱しなかった。私にとって女性に対する愛は常に、心清める思慕であった。
(「ヘッセ全集1 郷愁」高橋健二訳 新潮社 1982年より「郷愁」P.23)
ヘッセの書いたこの一文は何度反すうしてみても、甘美な気分、憧れの気持ちを呼び醒まさずにはいない。ここに表されているのは少年時代の初恋の感情であり、その背景として物心つき始めたときの世間に対する好奇心や、将来に対する漠然とした不安と理想主義的な潔癖さなどの入り混じった心理がある。
「郷愁」(”Peter Camenzind” 1904)、「車輪の下」(”Unterm Rad” 1906)等の作品でヘッセはこのように多感で傷つき易い少年の心を描いた。一般にヘッセに対して抱くのはこのような叙情派作家としてのイメージであると思う。しかし、ここで描かれているのはヘッセ自らの少年時代であって、いわばエリートコースから逸脱せざるを得なかった少年の屈折した内面であった。彼は自殺未遂を繰り返すような極度に神経症的で、一方詩人を夢見るロマンティックな少年であった。ここにアウトサイダーしてのヘッセの原点があった。
その後は、インドへの憧れを主題にしたものや、西欧の没落感を踏まえて個人の精神的破綻を追及した作品が多く書かれた。第1次世界大戦中は、平和主義を唱えたため、ドイツで売国奴のように非難攻撃される。一方、妻の精神病が悪化、ヘッセ自身もノイローゼで苦しむ、こうして公私両面にわたる辛苦が、ヘッセをして心の拠りどころを求める道程へと向かわせしめ、ユング的な内面世界の追求者となったのである。ここで「デミアン」(”Demian” 1919)、「シッダールタ」(”Sidhartha” 1922)、「荒野のおおかみ」(”Der Steppenwolf” 1927)と、中期の三部作といわれる作品が著された。
荒野のおおかみ
「荒野のおおかみ」とは、主人公のハリー・ハラーが自分自身を蔑称したものである。ハリーは非市民的な知識人であり、自己軽蔑的なペシミズムに囚われている。文学ではゲーテやノヴァーリスやドストエフスキーなどに精神的関心を強く抱いており、音楽ではモーツァルトやヘンデルを好む。「私の青春の神であり、私の愛と尊敬の終生の目標であるモーツァルト」なのであって、モーツァルトは彼にとって精神的な永遠の美しさの象徴である。ハリーは、自分は精神病であると思って自虐的になっており、五十歳の誕生日が来たら自殺しようと決心していた。
ハリーは「魔術劇場 ―― だれでもの入場はお断り」「入場は ―― 狂人だけ!」という看板を幻影のように見た。彼は魔術劇場を求めて歩き回り、その途中「無政府主義者的夜の楽しみ!魔術劇場!入場は・・・・・・お断り・・・・・・」というプラカードを持った男から「荒野のおおかみについての論文、だれでもが読むものにあらず」という題の小冊子を手渡される。このなかでハリーについて客観的に論述してあった。彼が荒野のおおかみ的性質と、人間的な性質の二面性を併せ持った人間であること、自殺者としてのハリー、彼の非市民性(アウトサイダーとしての性質)等々、ハリーの自覚症状を分析する。次にハリーの精神病、自殺願望、自己軽蔑の態度をより広い視野から否定し、「人間はけっして固定した永続的な形体ではない、人間はむしろ一つの試み、過渡状態である。自然と精神とのあいだの狭い危険な橋にほかならない」と、肯定的な人間観を訴える。これはハリーが孤立感からの解放へと向かうきっかけとなった。
彼は自殺しようとしてしきれなかった晩、うろつき回って一軒のレストランに入る。そこで不思議な少女ヘルミーネに出会う。彼女もまた厭世的、悦楽的に生きている娼婦であるが、ボーイッシュな清純な魅力を持ち、聡明である。ヘルミーネはハリーの魂の導き手となって様々な命令を下すが、最後には自分を殺して欲しいという。彼女はハリーにダンスをレッスンし、ジャズに親しませる。ジャズバンドでサックスを吹く青年パブロや、ハリーの恋の相手に官能的なマリアを紹介する。こうしてマリアとの愛と、それを支えるヘルミーネによって彼はいっときの幸福に浸る。
仮想カーニバルの晩、ハリーはマリアに別れを告げ、本当に求めるヘルミーネの姿を追った。彼女と踊り明かした後、ヘルミーネとパブロによって魔術劇場に案内される。ここでハリーは様々な幻覚を体験する。
一つは、戦場で自動車狩りが行われている場面、これは「ブリキの安物文明世界を全面的に破壊する道を開くべく努力している戦争」であった。次に、自分の人格が無数の将棋のこまとなり、将棋さしが様々な局面を随意に形作るさまを見る。サーカスで人間使いのおおかみによって猛獣のように扱われる人間ハリー。少年時代に遡り、初恋の少女と過ごす平穏なひととき。過去のすべての女性遍歴。そしていよいよ彼岸の世界に辿りつく。「ドン・ジョバンニ」の音楽が流れるなか、モーツァルトに出会う。モーツァルトは指揮して月や星を操っている。一方、下界の世界ではブラームスが数万人の黒衣の男の大きな列 ―― ブラームスの総譜(スコア)の中で無用だとされたような声部や音符の演奏者 ―― をひきずり、救いを求めている絶望的な光景が見える。ワグナーも同様に荷やっかいな連中がすがりつくなか、ぐったり足をひきずって歩いている。モーツァルトは言う
「あまりに楽器を用いすぎ、あまりに材料が浪費されすぎている」、「楽器を持ちすぎるのは(中略)ワグナーの個人的欠点でもブラームスの個人的欠点でもない。その時代の誤りだったのだ」。
(「ヘッセ全集7 シッダールタ」高橋健二訳 新潮社 1982年より「荒野のおおかみ」P.258)
こうした混沌とした幻想の後、ナイフを手にしたハリーはヘルミーネを殺す。やがてハリーの死刑執行となる。「ユーモアを解せぬ態度で魔術劇場を自殺期間として利用する意図を示した」罪状でハリーは永久に生きる罰に処せられ、一度徹底的に笑いものにされるという罰を受け、裁判の臨席者全員が高笑いをする。こうして絶望から自殺の試みに始まったハリーの冒険は、生の肯定に終わる。
映画「ステッペンウルフ」
「荒野のおおかみ」はフレッド・ハインズ監督・脚本で映画化された(1974年 アメリカ・スイス合作)。これが渋谷パルコ劇場のナイトシアターで7月18日よりロードショー後悔される。これのプレミア上映を観てきた。
果たして映画化できるような作品だろうかと疑問であったが、思ったより原作に忠実で、難解な原作がストーリーのうえではわかり易くなっていた。
主演のマックス・フォン・シドー(ハリー・ハラー)とドミニク・サンダ(ヘルミーネ)は好演。導入部あたりのハリーの神経症的気分がよく出ている。適度に暗く怪奇的で不条理な雰囲気が立ちこめている。それがヘルミーネとの出会いの後から原作になく明るい印象にかわっていく。ヘルミーネとショッピングを楽しんだり、ダンスのレッスンを受ける場面などはメロドラマ的な甘さに満ちていて、ハリーの深刻さが影をひそめてしまう。しかもヘルミーネ役のドミニク・サンダのとても若い清楚な美しさに魅せられてしまった。私としてはこのあたりの場面では、「荒野のおおかみ」に感じられた暗さや悲壮感よりも、むしろ前述した「郷愁」「車輪の下」あたりの感傷的な甘美さに満ちていると思った(この映画を観るまでは、私は「荒野のおおかみ」と、「郷愁」「車輪の下」等の作品をまったく別のものと捉え、両者の共通項としてオカルト的な「デミアン」を位置付けていた。ところが今回「荒野のおおかみ」がヘッセの混沌とした精神ばかりでなく、いかに憧れと、甘美に満ちた叙情的作品であるかを認識した)。
「荒野のおおかみの論文」はアニメ、魔術劇場のイメージはビデオを駆使した電子映像で表現している。とくに魔術劇場ではウォルト・ディズニー的なファンタジーになってしまい、フュージョン的な音楽も相まって、明るくなり過ぎたきらいがある。もっと時代がかったもやけた雰囲気が欲しいように思ったが、この点は賛否両論であろう。魔術劇場に到るまでの流れからしてみるとかなり違和感があった。
私の原作から受けたイメージとの食い違いは大きかった。ヘッセ自身の文明風刺や理想主義の観念がまったく抜け落ちている。特異なストーリーの上辺だけをさらって、映像の娯楽に走りすぎているのではないか ―― しかし、こう思う自分自身こそ魔術劇場においてハリー・ハラーの二の舞になっている。映像のユーモアを解していないのではないかと心によぎる。やがて、死刑執行の場面、最後に罰として一同の前に高笑いの的とされるのは、ハリーではなく、余りに観念的に見入っていた自分自身なのであった。
※文中の引用文は高橋健二訳「ヘッセ全集」新潮社版による
※ヘッセ評伝としては高橋健二著「ヘルマン・ヘッセ ―危機の詩人―」
新潮選書を参考にした。
映画「ステッペンウルフ」予告編
「ブーレーズ作曲家論選」 [本]
「ブーレーズ作曲家論選」
ピエール・ブーレーズ著/笠羽映子訳(ちくま学芸文庫)
を手に入れたことである。
これが370ページほどの文庫本にしては1400円と異常に高い!ふつうの文庫本ならのこの半額くらいだが、本の性格上、一般的な音楽啓蒙書の域を超えているので、やむを得ないのだろうか。
序章(テクスト、作曲家とオーケストラ指揮者)
J.S.バッハ
L.v.ベートーヴェン
H.ベルリオーズ
R.ヴァーグナー
G.ドビュッシー
A.ヴェーベルン
A.シェーンベルク
I.ストラヴィンスキー
A.ベルク
J.ケージ
の各章で構成されているが、1冊の本としての書き下ろしではなく、作曲家/指揮者のブーレーズが発表した論文、論評、エッセイ、散文詩(のようなもの)、手紙などを寄せ集めた本である。
それだけに各章ごとに難易度のバラツキが大きく、サラッと読みこなせる章もあれば、まともに読み進められない章もあった。
「ストラヴィンスキーは生きている」は100ページほどの論文で、「春の祭典」を数多くの譜例をあげながら細かにその複雑なリズム構造を中心に分析している。
例えば冒頭のファゴットのソロによる不思議な旋律は、実にややこしい変拍子と音価(譜割り)で反復的・対称的な音形で成り立っていることが解説されている(冒頭だけは何とかついていけた...)。
しかし列挙された譜例がボクの記憶している曲のどの部分か照合がつかないので、譜面を見ただけで頭の中に音を鳴らせるような能力のないボクにはスラスラ読めない。
いずれ「ハルサイ」のスコアを買ってよくCDを聴いてスコアリーディングを重ねたうえで、数式いっぱいの物理や数学の本のようにじっくりと読み解きたい。
かつて大学オケの先輩が「ハルサイ」のスコアリーディングしているのが知的でカッコよく思えたが、この楽曲の本質に近づくためにはそのようにして複雑な変拍子の組み合わせのリズム構造をパズルを解くように理解できるようにしたいと思った。
『ペレアスとメリザンド』のための鏡...と題された章は、ボクが最近よくこのオペラのCDを聴いていて、ブーレーズ演奏のDVDも観ていただけに、面白く読めた。
このドビュッシーの唯一の(完成された)オペラの成り立ちには、ワーグナーの影響や反発ぬきには語れないこと。
演奏論としては、(いかにもフランスのエスプリ的に)過度に慎み深い演奏が行われるが、実はダイナミックに演奏されるべきこと。
ボクがカラヤンのCDで感じた歌手起用でペレアスとゴローの違いが明瞭でなかったが、ブーレーズは歌手起用にも言及していただけあってDVDではペレアス(テノール)とゴロー(バリトン)の声質の違いが明瞭であったことなども合点した。
他の論評も易しくはない。訳も専門用語や固い語彙を並べたような直訳調が鼻について頭に入ってこない。おそらくブーレーズの原文も論文調で難しいのだろう。
しっかり理解しようとすれば音楽理論の知識も必要なようで、音楽辞典や百科事典などで様々な用語を事細かく調べながら読む...という根気がないボクは、宿泊先のベッドの上や新幹線の中で活字の上辺だけでもざっとなぞるように読み終えた。
それでもビジネス書ほどは眠たくならずに読み進められたのは、関心ある作曲家・楽曲のアウトラインや、敬愛する指揮者ブーレーズの音楽観の一端に触れられたように思ったからだ。
各章の作曲家は、常に新ヴィーン楽派の作曲家(シェーベルク、ベルク、ウェーンベルン)やワーグナーとの比較・比喩や関連のなかで語られている。
やはりブーレーズが自家薬籠中のものとしている前衛音楽を出立点としていかにレパートリーを広げ、楽曲分析してきたかが見てとれる。
だから一般的な音楽読み物としては難解過ぎ、片寄り過ぎるのであるが、ブーレーズに関心のある方や「現代音楽」ファンには一読の価値があるだろう。
ボクが学生の頃は、CBSソニーの分厚いクラシックLPのカタログ冊子がクラシック音楽入門のバイブルのような存在であった。そのなかでも、ともに指揮者兼作曲家で活躍していたバーンスタインとブーレーズ(ともにニューヨークフィル音楽監督を歴任)がアンチカラヤンの二大ヒーローでもあった。
作曲家としては、「ウエストサイドストーリー」で親しめるバーンスタインに対して、前衛音楽のブーレーズは近づき難い存在であった。
だが指揮者としてのブーレーズはボクが最も敬愛・愛聴してきた音楽家で、いちばんたくさんCDを収集した演奏家である。
ボクにとって、ストラヴィンスキー、ラヴェル、ドビュッシー、バルトークなど近代のオーケストラ曲はブーレーズの演奏なしでは考えられない。
主旋律を甘美に強調したり、感情移入で歌い上げる「親しみやすい」演奏とは対極にあって、各声部を絶妙のバランスでコントロールして「スコアが透けて見えるように」と喩えられる透明感のある美しい音響=音楽を聴かせる指揮者である。
ボクは脂っこいイメージで苦手だったマーラーもブーレーズだから入門できた。
ブーレーズは「理系頭」代表格のような指揮者・作曲家で、合理性や論理性を重視した客観的で冷徹な演奏家のイメージが強かった。
しかし本書ではブーレーズ自らが、合理性や論理性と主観との対決という不確実なもの・不安定で神秘的なものがあるからオーケストラの指揮が面白いと述べている...すなわち自らの主観性や曖昧さを認めているところが意外でもあり、納得もできた。
ちなみに本書を読みながら、出張中はWALKMANに入れていた指揮者ブーレーズの演奏を集中的に、できるだけ広い年代におよぶ選曲で聴いた。
(1)ヘンデル:「水上の音楽」組曲/「王宮の花火の音楽」組曲
ニューヨークフィルハーモニック
(2)http://www.hmv.co.jp/product/detail/2780372[モーツァルト:セレナード第10番『グラン・パルティータ』
ベルク:ピアノ、ヴァイオリンと13の管楽器のための協奏曲]
内田光子(ピアノ)・クリスティアン・テツラフ(ヴァイオリン)
アンサンブル・アンテルコンタンポラン
(3)http://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3-%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%9B%B2%E7%AC%AC5%E7%95%AA-%E3%80%8C%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%80%8D%E4%BB%96-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A2%E7%AE%A1%E5%BC%A6%E6%A5%BD%E5%9B%A3/dp/B00005G888/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=classical&qid=1275138989&sr=1-1[ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」
カンタータ「海の静けさと幸福な航海」]
ニューフィルハーモニー管弦楽団
(4)ベルリオーズ:「幻想交響曲」/「トリスティア」
クリーヴランド管弦楽団
(5)マーラー:交響曲第2番「復活」
ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
(6)マーラー:交響曲第3番
ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
(7)マーラー:交響曲第8番「千人の交響曲」
シュターツカペレ・ベルリン
(8)ドビュッシー:交響詩「海」/「管弦楽のための『映像』」他
ニュー・フィルハーモニア管弦楽団/クリーヴランド管弦楽団
(9)ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」/「春の祭典」
クリーヴランド管弦楽団
(10)シェーンベルク:「浄められた夜」/ベルク:「叙情組曲」
ニューヨークフィルハーモニック
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」
ピエール・ブーレーズ指揮 パリ管弦楽団




